永楽善五郎の可愛いお皿を買取させて頂きました【都をどり 皿 5客】

千代屋では、京都の名窯である永楽善五郎の陶器を高価買取しております。今回は、京焼・清水焼の名作「都をどり 皿 5客」を買取させていただきました。
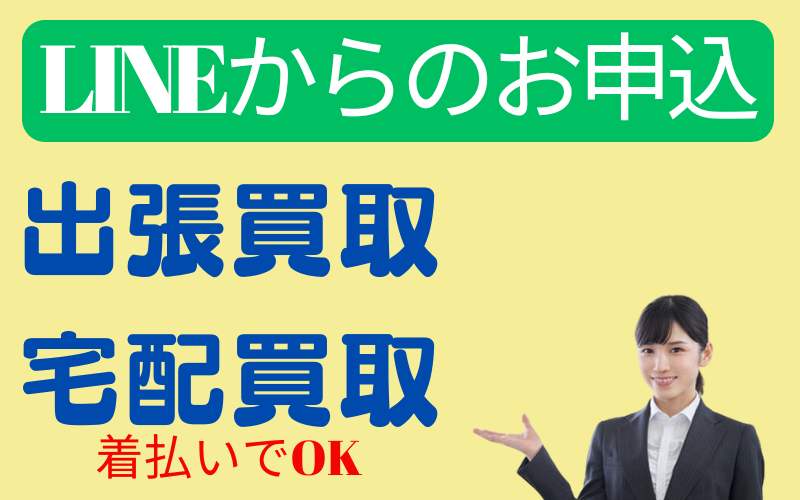 |
  |
永楽善五郎とは?その歴史と魅力
京焼・清水焼の名門 永楽家とは
永楽善五郎は、京都の伝統的な焼き物「京焼・清水焼」を代表する名工のひとつです。永楽家は室町時代から続く窯元で、茶道具や食器を中心に制作しており、多くの茶人や文化人から愛されています。
永楽善五郎の代表作と特徴
永楽善五郎の作品は、上品な色彩と洗練されたデザインが特徴です。特に茶道具は高い評価を受けており、千代屋でも多数の買取実績があります。
今回買取した「都をどり 皿 5客」とは
都をどりとは?京都の伝統文化
「都をどり」は、京都の花街・祇園で春に開催される舞踊公演です。その華やかさをモチーフにした陶器が「都をどり 皿」で、美しい絵柄と京都らしい優雅な雰囲気が特徴です。
都をどり 皿のデザインと価値
今回買取させていただいた「都をどり 皿 5客」は、繊細な色彩と職人技が光る逸品でした。保存状態が良く、共箱も揃っていたため、高価買取が実現しました。
永楽善五郎の茶道具・陶器の買取市場
永楽善五郎の作品はなぜ高価買取されるのか
永楽善五郎の陶器は、美術的価値と実用性を兼ね備えており、特に茶道具の市場では高い人気があります。希少性の高い作品や、共箱付きの品は高価買取が期待できます。
茶道具の買取市場の動向
近年、茶道具の市場は国内外で注目されており、特に京焼・清水焼の人気が高まっています。千代屋では、専門の査定士が市場の動向を踏まえた適正な価格で査定いたします。
千代屋の買取サービスについて
千代屋が選ばれる理由
千代屋では、陶器や茶道具の買取において豊富な経験を持つ専門査定士が対応し、適正価格で買取いたします。また、出張買取・宅配買取の両方に対応しており、お客様のご都合に合わせた買取が可能です。
専門査定士による高額査定のポイント
永楽善五郎の陶器や茶道具を高く売るためには、専門知識を持った査定士による正確な査定が重要です。千代屋では、作品の状態や市場価値を的確に判断し、最適な価格をご提案いたします。
永楽善五郎の買取方法
出張買取の流れ
千代屋では、お客様のご自宅まで訪問する「出張買取」を行っております。事前にお電話またはLINEで査定をお申し込みいただき、査定士がその場で査定・買取を行います。
宅配買取の流れ
遠方のお客様には、宅配買取をご利用いただけます。LINEで簡単査定後、着払いで商品をお送りいただき、査定完了後にご指定の口座へお振込みいたします。
永楽善五郎の高価買取のコツ
保存状態が査定額に影響
陶器や茶道具の買取では、保存状態が査定額を大きく左右します。ヒビや欠けがないかを確認し、できるだけ良好な状態を保つことが重要です。保管の際は湿気を避け、柔らかい布で優しく拭くと良いでしょう。
共箱・証明書の重要性
永楽善五郎の作品には、作家名が記された共箱や証明書が付属していることが多く、これが査定額を大きく左右します。共箱があることで真贋の確認が容易になり、市場価値が高まるため、できるだけ付属品を揃えて査定に出すことをおすすめします。
茶道具の買取と査定ポイント
高く売れる茶道具の条件
茶道具の中でも、特定の作家や名工による作品は高価買取が期待できます。特に「永楽善五郎」や「楽焼」「京焼」の作品は市場での需要が高いため、適切なタイミングで売却することでより良い価格がつく可能性があります。
査定でチェックされるポイント
査定時には、以下のポイントが重要視されます。
- 作家名や窯元の確認(永楽善五郎の刻印など)
- 作品の状態(傷や汚れ、欠けの有無)
- 付属品の有無(共箱、証明書、仕覆など)
- 市場での需要(流通価格や人気の傾向)
これらの要素を考慮し、最適な査定額をご提示いたします。
お問い合わせ方法
お電話からのお問い合わせ
お急ぎの方は、お電話にてお問い合わせください。専門スタッフが対応し、買取のご案内をさせていただきます。
LINEからのお問い合わせ
LINEを利用した簡単査定も可能です。写真を送るだけで事前査定ができるため、忙しい方にもおすすめです。
永楽善五郎の茶道具・陶器をお持ちの方は、ぜひ千代屋の無料査定をご利用ください。確かな査定力と豊富な経験で、大切な品を適正価格で買取いたします。
関連する買取情報
千代屋では、永楽善五郎の陶器や茶道具以外にも、さまざまな骨董品やレトロ商品を買取しております。以下のページもぜひご覧ください。
京焼、永楽善五郎関係のリンク
永楽善五郎や京焼・清水焼についての詳細な情報を知りたい方は、以下のサイトも参考にしてください。
- 京焼・清水焼協同組合(京焼・清水焼の歴史や作家情報)
- 裏千家公式サイト(茶道具や茶文化について)
千代屋では、骨董品・茶道具・レトロ商品の査定・買取を行っております。ご不要になった品がございましたら、ぜひお問い合わせください。
永樂善五郎の歴史と代々の歩み
永樂善五郎(えいらく ぜんごろう)は、京都を代表する陶芸家の家系であり、千家十職の一つ「土風炉・焼物師」として知られています。初代から現在に至るまで、茶道具や陶器の制作を通じて日本の茶文化に大きく貢献してきました。
初代から九代目:西村姓と土風炉師としての始まり
初代・西村宗禅(?-1558年)は、奈良の西ノ京に住み、春日大社の供御器を作る職人でした。二代目・宗善(?-1594年)の頃、茶の湯が広まり、武野紹鴎から土風炉の注文を受けるようになり、堺に移住しました。三代目・宗全(?-1623年)は千家からの依頼を受け、京都に移り住みました。以降、九代目・宗巌(?-1779年)まで西村姓を名乗り、主に土風炉の制作に従事しました。
十代目・了全(1770年-1841年):永樂家再興の礎
九代目の早逝により、幼少で家督を継いだ了全は、1788年の天明の大火で家屋や資料を失いました。しかし、表千家や樂家の支援を受け、土風炉だけでなく茶陶の制作にも取り組むようになりました。
十一代目・保全(1795年-1855年):永樂姓の由来
1827年、紀州藩主・徳川治宝の招きで西浜御殿の御庭焼開窯に参加し、「河濱支流」の金印と「永樂」の銀印を拝領しました。これ以降、「永樂」の印章を使用し、十二代目・和全(1822年-1896年)の代から永樂姓を正式に名乗るようになりました。
十四代目・得全(1852年-1909年)と妙全(1852年-1927年):永樂家の支え
得全は、三井家や鴻池家の庇護を受け、多くの作品を残しました。彼の急逝後、妻の妙全が家業を継承し、茶道復興期に多くの茶道具を制作しました。妙全の作品には「善五郎」と記し、朱で「悠」の字を押印したものがあり、「お悠さんの朱印」として親しまれています。
十六代目・即全(1917年-1998年):近代の名工
即全は、18歳で家督を継ぎ、神奈川・大磯に城山窯を築きました。京都伝統陶芸協会の初代会長を務め、数々の文化賞を受賞するなど、伝統陶芸の発展に尽力しました




